第67話 ひとごろし
第66話のおさらい
伯母の執拗な誘いに根負けした静一は、伯母の車の助手席に乗り込んでいた。
車を発進させた伯母は、寄り道だと言って長部家に真っ直ぐ向かうルートから外れて車を走らせる。
あの夜以来、しげるは劇的に回復していた。
そして山の上で何があったのかを伯母に語っていたのだった。
伯母は静一に、崖の上でふざけてバランス崩したしげるを助けようと駆け寄ったが、間に合わず落ちたという、静子の証言をとしげるの言っていたことが違うと続ける。
しげるは、崖の上でふざけてバランス崩していたら、駆けてきた静子に一度は抱きとめられた。しかしそのあと、にっこり笑顔を浮かべたかと思うと崖下に突き落とされたのだと主張していたのだった。
そして本当のことを言って欲しいと迫る伯母に対して、静一は睨みつけて、静子は嘘をついていないと突っぱねようとする
「本当に?」
しかし伯母は全く動じることなく、静一を見つめる。
静一はその伯母の迫力に呑まれていた。
そして伯母は、あの夜、静一が自分を非難した、静子に対した過保護と言っていたことに関して、静一が心配だったからそう言っていたのだと話し始める。
静子は常に静一にべったりとくっつき、静一がしようとすることを全て先回りでやってあげていたのだと伯母。
そして伯母は、静一が3歳くらいの頃に負っていたケガについて、静子に何かされたのではないかと静一に問いかける。
その伯母の質問で、静一は幼少期に静子と道端の猫の死体に触ったことを思い出していた。
猫の死体に触れた幼い静一の小さな右手に黒い模様が広がっていく。
静一は左手で右腕をぎゅっと握り、体中を震わせていた。
伯母は静一のことを守るから、本当のことを教えてくれと静一に迫る。
突如、伯母の左腕を殴る静一。
ハンドル操作に集中している伯母は必死にやめるように訴えるが、静一は構わず伯母の左腕を殴り続ける。
車が蛇行し始めたのか、後ろを走っている車がクラクションを鳴らす。
ついに我慢の限界に達した伯母が叫ぶ。
「やめなこの…ひとごろし親子っ!!」
伯母が車を停車させると、静一はすぐに外に飛び出して行く。
伯母は静一を呼び止めるが、構わず逃げていく静一。
静一は後ろを一切振り返らず、全力で伯母から逃げるのだった。
第66話の詳細は上記リンクをクリックしてくださいね。
第67話 ひとごろし
説明
すっかり日が暮れていた。
街頭が灯る住宅街を、息を切らしてひた走る静一。
自宅に辿り着くと、玄関に静子が立っている。
「遅かったんね。」
静子は静一をじっと見つめながら続ける。
「まさか、また吹石さんといたんじゃないでしょうね?」
静一は静子をじっと見つめたまま、一瞬の間を置いて否定する。
「……ちがう…ちがう…! おばちゃんが…!」
力尽きたように地面に膝をつく。
「え…?」
静子は息を切らして疲労困憊の様子の静一に、立ったまま声をかける。
「中、入りな。」
散らかったリビングには、クリスマスツリーが飾られていた。
静子は湯気の立った牛乳の入ったカップを静一に差し出す。
「おさとう入れたから。」
牛乳を飲んで一息ついた静一に、で? と静子が切り出す。
「何があったん?」
静一は車に乗った伯母が学校帰りの自分に送っていくから乗れと声をかけてきたとその時の状況を説明し、伯母の目的が純粋に自分を自宅に送るためではなく、自分を問い詰めるためだったと答える。
何を? と静子に先を促され、静一は答える。
「しげちゃんが…喋ったんだって。……あのときの…ことを……」
「なんて?」
静子に問われた静一は答える。
「つきとばされたって…言ったんだって。ママに。」
それを受けて静子は一瞬驚いた様な表情を浮かべるが、すぐに微笑む。
「それを…おばちゃん信じちゃったんだよ。ウソなのに。」
「僕に…見てたんだろって。本当のこと言えって…脅迫してきたん!」
「…ぼっ!」
笑みを浮かべようとするが、中途半端に歪んだ表情になる静一。
「僕らのこと…”ひとごろし親子”だって……」
笑う静子
静子は微笑んだまま、黙って静一の話を聞いていた。
静一の話が途切れると、ゆっくりと歯を剥き、さも楽しそうに笑って見せる。
「あは…あはははははははっ」
静子の意外な反応に、静一は静子を見つめたまま言葉を失っていた。
「はー…そう… そっかあ……」
ひとしきり笑い終えて静子は笑顔のまま静一に訊ねる。
「それで? それだけ?」
静子に話を促された静一は、猫の死体に触れた幼い頃の自分の小さな手に黒いシミが生じた映像を思い出していた。
「あと…あ…と…」
静子に合わせるようにぎこちない笑顔を浮かべる静一。
「僕が…3歳んとき………ケガ…してたって…」
静一は視線を下に落としていた。
「…本当?」
そう問われ、静一は顔を上げて静子を見つめる。
静子は視線を不自然に右上にそらしていた。
静一の顔からぎこちない笑顔が消え去る。
「もうみんな…知ってるんかな?」
うっとりとした表情で呟く静子。
「…え?」
「お義父さんもお義母さんも、お義兄さんも…………一郎も。」
「みーんな、私達が悪者のひとごろしだって。思ってるんかな?」
「けいさつが…つかまえに来るんかな?」
「そしたら私…やっと出ていけるんかな? この家も。ぜんぶから。ぜーんぶ。」
静子は頬杖をついて、楽しそうな笑顔を浮かべる。
「いつくるかなあ? いつ私を連れ出してくれるかなあ?」
「あー楽しみ! うふふふふっ!」
ゆるさない
呆然と静子を見つめている静一に静子が問う。
「静ちゃん、静ちゃんはどうする? ママがいなくなっちゃったら、パパたちと生きて行ける?」
テーブルに突っ伏すように体を預けながら、静子は微笑を浮かべて静一を見つめる。
「いやだ…」
大粒の涙をボロボロと零す静一。
「いやだ…ママが…悪者にされるなんて…ママが…つかまるなんて…」
静子は目を細めて、静一をじっと見つめている。
「そんな…そんなことになったら…僕は…」
「僕はあいつらを…ゆるさない…!」
テーブルに突っ伏し、目を細めたまま静子が問いかける。
「ゆるさなかったら…なにしてくれるん?」
その質問を受け、静一は一瞬固まる。
「ゆるさな…かったら………」
具体的な答えを返すことができず、確認するようにそう呟くのが精一杯だった。
「ママはね、何もできなかった。ただずーっと。この家で。一郎と静ちゃんの世話してただけ。ゆるせないって思いながら。」
遠くを見つめるように視線を上げる静子。
「ぜんぶゆるせないの。だから消えちゃうしかないの。私は。」
静一は静子のそばに近寄ると、彼女の背後から、そっと支えるかのように体に手を添える。
「ママが消えちゃうなら…僕も一緒に消える。」
静子をじっと見つめて、確かな口調で誓う静一。
「ママ…」
静一は目を伏せたままの静子をじっと見つめていた。
感想
主体的に動こうとしない静子
自分がしげるを殺しかけたことがバレて、捕まればここから出て行ける。
静子が言ったことは、うどん屋で一郎や静一の前で呟いたことと同じだ。
今回の話で静子のあの時の呟きは気の迷いなどではなく、一貫性のある主張であることが確定したわけだ。
なんか静子の言っている内容は発想が突飛で、あまりにも病んでるなぁと思った。
ブラック企業で過重労働に追い込まれた人が、事故に遭えば、あるいは電車に飛び込めばもう会社に行かなくて済む、と窮屈な思考をしてしまうのに似ている。
今の自分の置かれた環境が嫌なら離婚して出て行けばいい。
でも静子はそれを実行せず、自分から主体的に動くことなく、何かが自分の人生に介入してくるその時をじっと待っていた。
静子の抱えている闇の一端が徐々に見えてきたように思う。
要は静子は自分が人生を打開する力を持っていると全く信じていない。
無力感とそれに伴う閉塞感が常に彼女を支配している。
彼女がそのような状態に追い込まれてしまっている理由として考えられるとしたら、ひとつは逃げ込める実家が存在しない、とかかな。
すでに静子の父も母も生きていない。もしくは生きているけど絶縁状態でとても戻れないとか?
あとは就職に関して強い不安を持っている?
作中の舞台1990年代前半くらい。2020年現在に比べればまだまだ女性が仕事に就ける機会は男性に比べれば少なかったり、仕事があっても給与が安かったりした時代だ。女性が全くの独力で生きていくのはハードだし、それにもし高校を中退していたりしたらさらにキツイと思う。
静子は両親から愛を受けなかったと言っていたから両親が健在でも実家がシェルターとして機能しないと考えられるし、また、学生時代にきちんと社会に出るための力を蓄えられるような満ち足りた生活が出来ていたとは考え辛い。
結局静子の抱えている問題の根幹には、親からの愛の不足があるのかもしれない。
上記は妄想だが、可能性は排除できない……。
このまま一郎と静一の世話をしながら、一郎の両親や伯母夫婦、しげると関係を維持し続けていかなくてはいけない人生に絶望している。
かといって他に逃げ込む場所もなく、自分の力のみで生きていける力があるわけでもない。
不満しかない状況に対して何も出来ない無力感と、しかしここから逃げ出す術もなく用意された役目をこなさざるを得ない閉塞感に静子は疲れ切ってしまったのではないだろうか。
もはや自分から何をどうしようとも考えられず、ただその時その時を心を殺して生きている……としたら何て哀しい人生なのか。
望むのは今の環境が壊れること。それは自分の死によっても達成される。
だから猫の死体を前に微笑んで見せたのかな……。でも自死を選ぶ気力もないとか?
自分から動いても無駄だと思い込んでいる人は、「自己効力感が低い」状態というらしい。
それは自己肯定感の低さにも直結する。
しげるを突き落とした時の微笑みの意味は、これで自分の人生が変わるという予感だったのかな……。
少なくとも静子が健全な思考とは無縁であることはわかる。
そんな状況に追い込まれた静子に同情したらいいのか、それともヤバイ奴だと切って捨てるべきなのか……。
静一は静子を守るために狂暴性を増していく
静一は静子がしげるを突き飛ばしたのを自分の目で見たはずだった。
しかし伯母に対してそれを強く否定したように、もう静一には静子の犯行を認めることは出来なくなってしまった。
もちろん、それは静子から受けた洗脳がきっかけではあると思う。
しかし何よりも、もはや自分には静子以外に大切なものがなくなってしまったと感じていることが原因として最も大きいのではないか。
そもそも静一は静子を守らなくてはいけないと考えて、警察に嘘を吐いた。
静一は最初から静子の味方だった。
一時は静子に反発したものの、それでも静子がしげるを突き落としたことを誰にも漏らさなかった。
そして静子とのやくそくを守るために何もかも失った今、自分がやるべきことは何としても静子を守ることになった。
つまり彼女の犯行を絶対に認めず、どこまでも母を守る立場になったわけだ。
伯母の家でしげるや伯母を突き飛ばしたし、小倉を殴りつけ、前回は運転中の伯母を叩いて危うく事故を誘発しかける。
ここ最近の静一の暴力性の発露は、彼が追い込まれてどうしようもなくなっていることを意味していると思う。
今回、涙を流しながら「僕はあいつらをゆるさない」と言った静一から、これまで以上にやらかしそうな危険な雰囲気が漂ってくる。
それに対して冷静な静子……。まるで静一の自分への愛を試しているかのようだ。
これからこの母と子はどうなってしまうのだろう。
以上、血の轍第67話のネタバレを含む感想と考察でした。
第68話に続きます。
あわせてよみたい
押見修造先生のおすすめ作品や経歴をなるべく詳細にまとめました。
血の轍第5集の詳細は以下をクリック。
血の轍第4集の詳細は以下をクリック。
血の轍第3集の詳細は以下をクリック。
血の轍第2集の詳細は以下をクリック。
血の轍第1集の詳細は以下をクリック。



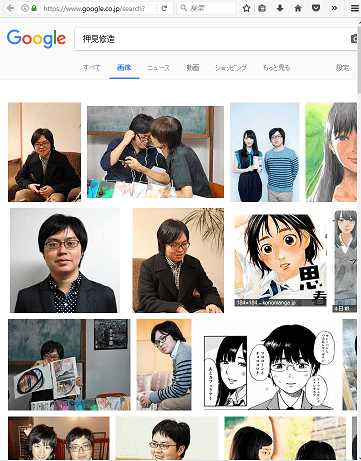



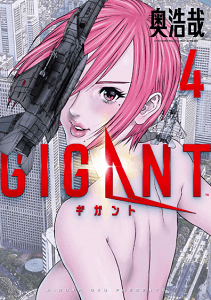





コメントを残す