第64話 高台
第63話のおさらい
静一と教師の待つ一室に小倉とその母親が到着する。
右目に眼帯をして俯いている小倉とは対照的に、母親は穏やかな表情で教師に挨拶をする。
小倉と母親が座ると、静一は教師に何かいうことはないのかと促される。
静一はしばらく黙って俯いたままだったがやがて、お母さんが来るまで何も言えないです、と答える。
教師に謝罪を促されても静一は、できません、と表情を変えることなく答えるのだった。
小倉の母親は優しく、あの大人しい長部君がこんなことするなんて信じられなくて、と静一に話しかける。
そして小倉の説明では、みんなで遊んでたら急に静一が怒って殴ってきたと聞いていると続ける母親。
静一の表情は変わらない。
静子は到着するなり即座にその場に崩れ落ちるように土下座をする。
「……なんて…おわびしたらいいか……ごめんなさい…私のせいです……ごめんなさい…!」
ケガは大したことなかったですから、と鷹揚な態度を見せる小倉の母親。
しかし静子は立ち上がることなく、そのまま謝罪を続ける。
教師に椅子に座るよう促されても、このままでいいです、とその申し出を断る静子。
話ができないので座って下さいと教師に言われ、ようやく静子は静一の隣の椅子に座る。
そして改めて教師から、何があってこんなことなったの? と事情の説明を求められた静一は静子が自分と目を合わせて頷いたのを機に話し始める。
一人でトイレにいたら小倉、蛭間、酒田が入ってきて、ふざけて髪の毛をグシャグシャにされてしまったことと説明する静一。
しかし静一の説明は予想外の方向へ進んでいく。
「死んでるくせに。みんな…全部…死んでるくせにって…思って…」
「だからどうだっていい。どうせまぼろしだから。ごみだから。」
静一はまるで笑うように口元を歪ませる。
「だから、なぐった。」
その説明に、目を細める静子。
静一の話が良く分からず、教師は思わず聞き返す。
「長部…何…言ってるん…?」
小倉と彼の母親もまた、呆気にとられたような表情で静一を見つめていた。
「先生。」
静子が口を開く。
「吹石由衣子ちゃんのせいです。」
静子は、吹石が静ちゃんをたぶらかしていたと主張する。
毎日放課後二人で歩いて、家にひっぱりこまれて変なことした挙句汚されてしまったストレスが原因なんだと静子は続ける。
「心はだいぶ戻ったけど…まだ全部はキレイになってなくて。」
静一に視線を向けて問いかける静子。
「そうだいね? 静ちゃん。」
「はい。」
静一が笑顔を浮かべる様子を、小倉の母親は黙って、呆然と見つめていた。
第63話の詳細は上記リンクをクリックしてくださいね。
第64話 高台
お開き
話し合いを終えた一同は廊下に出る。
今日はこれで、と場を締める先生。
「本当に…申し訳ありません。」
静子は小倉母子に頭を下げる。
「後日きちんと謝りに伺いますので……」
大丈夫です、うちの子も悪かったんですから、と小倉の母。
小倉は、目を伏せて黙っている静一をじっと睨んでいる。
「先生あの…先程言ったこと…考えて下さい。」
「え?」
先生は何のことかわからないという表情で静子の言葉を聞き返す。
「吹石由衣子ちゃん、別のクラスにしていただけないかって事。」
静子は極めて真剣に、真っ直ぐに先生を見つめる。
「お願いします。静一は被害者なんです。」
「あの…それは、」
微かに困ったような笑みを浮かべる先生。
「吹石さんの親御さんにも聞いてみますので。まだあらためて。」
そして先生は小倉の母親ともう少し話があるから、と静子と静一に帰宅を促す。
「…はい。」
素直に聞き分けて、頭を下げる静子。
「失礼致します。」
静子と静一は廊下を歩き始める。
背中越しに先生と小倉母子の会話がわずかに聞こえてくる。
その内容まではわからないが、静一はふと気になって背後を振り返ると先生と小倉母子は静一たちを見ている。
静一の目には、彼女たちの冷たい視線は自分たちを疎ましく思い、拒絶しているように見えていた。
共感を示す静子
帰路を歩く静子と静一。
「ごめんなさい。」
静子に謝罪する静一。
「いいんさべつに。これからは気をつけな。」
静子は淡々と返したあと、さきほど先生からどうして殴ったのかと聞かれた時の静一の答えについて問いかける。
「みんな死んでるくせにって。どうせみんなまぼろしで、ごみだから。どうだっていんだって。あれは、どういう意味?」
静一は少し間を置いて口を開く。
「…僕…僕…は…」
「ママもね、おんなじ事考えてたん。」
答えようとした静一の発言を遮って切り出す静子。
静一は静子の横顔を見つめる。
「静ちゃんくらいんとき。中学生んときから。今でもそうかもしれない…」
「………僕…」
静一は微かに、寂しそうな笑みを浮かべる。
「僕…わかるよ。ママの気持ち。」
静子は静一に視線を移す。
「静ちゃん。ちょっと、寄り道しようか。」
記憶
二人は坂の入り口に差し掛かっていた。
「ここ。」
静子を先頭に、二人は坂を登り始める。
「ママがね。中学生んときよく行ったん。」
静子と静一は坂を登り、間もなく高台に到着していた。
高台から眼下の夜景を見る二人。
夜景を見ながら、ふふ、と笑う静子。
「へどが出らいね。この灯り全部ひとつひとつ家族が入ってて、いちいち生活して生きてるなんて。」
静一には隣で街を見下ろしている静子が、中学生の姿に見えていた。
「私はずっと、こっち側でいい。」
静一は静子をじっと見つめている。
「…って…思ってたんさ。」
静子は静一に視線を移す。
「静ちゃんが小さい頃にも、よくここへ2人で来たんさ。散歩しに。覚えてないやいね。」
見つめ合う二人。
静一は自分がまだろくに言葉も話せない頃、静子と一緒に高台に来た記憶を思い出す。
「…………覚えてる…」
「…ほんとう?」
静子に問われた静一は街を見つめて、涙を溢れさせながら答える。
「おぼえ…てるよ…」
どうして泣くのかと静子に問われ、静一は戸惑いながらも答える。
「わかんない。わかん…ないけど…哀しくって…」
「……そうだね。哀しいね…」
静子は静一を抱きしめる。
目を閉じる静一。
静子は静一をじっと見つめている。
ふと、幼少期に道端で見た猫の死体を思い出し、目を開く静一。
「……あの道…この近くだ…」
「ねえママ! ほらあの道!」
若干声を弾ませて静一は問いかける。
「小さい頃…猫の死体を一緒に見つけたあの道! あれこの近くだったいね!?」
静子はきょとんとした表情で静一を見つめている。
「ねぇちょっと行ってみるん…べ…」
静一は静子の表情から、先ほどよりも静子が冷めていることに気付く。
「……そうだっけ。それはママ忘れちゃったい。」
「…………あ…」
静一の顔から笑顔が消える。
「もう帰るんべ。寒いから。」
その場を後にする静子。
静一は遠ざかっていく静子の背中を見つめていた。
「…うん。」
感想
自分の正当性を疑っていない静子
冒頭から静子のモンスターペアレンツぶりが爆発してる。
吹石の別クラス異動に関して念を押しているあたり、極めて冷静に、超真剣に提案しているのがわかる。
一時の激情に駆られてのことなら、冷めた時に、さっきの話はなしで、みたいに自分から話を引っ込めることもあるんだけど……。
「静一は被害者なんです」
静子からすればこれはもう動かせない真実なんだなー。
前回の静子の態度からわかっていたけど、改めてそれを感じた。
確かに吹石の部屋で静一と吹石の二人の間であったことは、同年代の子供たちからしたらちょっとばかり進んでいるかもしれない。
だから親として心配するのは理解できる。でも先生に対してここまで要求するのか。
自分が静子の立場なら、ちょっと相談があるんですが、と二人きりで話すかなー。
それでも精々、どうしたらいいですかね? と本当にただ相談するに留めるけど……。
少なくとも静子みたいにここまでここまで堂々とした態度で吹石のクラス替えを進言できない。
まあ、男女が逆なら静子みたいな要求もまだわかるかな。
たとえば娘が同年代の男に襲われたみたいな話なら、静子の毅然とした態度は大正解なんだが……。
でも別に静一は襲われたわけではないんだよなぁ。
息子を誑かす女生徒を別クラスにしてほしい、と言った静子の気持ちが分かる母親の方もいるだろう。
でも”気持ちが分かる”ことと”実際に行動する”とでは、そこには天と地ほどの差があるから気にしなくてもいいと思う。
しかし先生のリアクション、困り方が実にリアルだと思った。
真剣な表情で聞くのではなく、微妙な笑みを浮かべながらも、しっかり理解しましたよ、善処しますよという態度はきちんと見せていくこの感じ。
先生も社会人なんだよなぁ、と思った。
かつて店頭で販売員として働いていた頃のクレーム気味のお客様対応中の自分もこんな感じだったかも。
無理です! とは決して言えない辛さ、悲しさ、やるせなさを思い出した。
この話は90年代が舞台で、確かまだこういう困った親をモンスターペアレンツとは呼称していなかったはずだ。
でもそんな言葉が無かった頃から確実にいたはずなんだよな、こういう親は。
ただモンスターペアレンツという言葉が広まり始めた頃よりは可視化されなかったはずだし、実際少なかったと思う。
90年代中頃だと、まだ学校に物申すのではなくガマンする人が多かったんじゃないか。
だからこそ静子の”女子生徒を別クラスにしてくれ”という真剣な要求の異常さが際立つと思う。
小倉母子が見ているというのにそんなこと一切おかまいなしに発言できるのがすごいわ。
自分なら、という感じで前述したけど、せめて先生と一対一になって相談するような内容だろ……。
モンスターペアレンツは自分の要求の正当性を信じて疑わない。
だから、むしろ静子としては全校生徒の前で声を大にして吹石の悪女ぶりを喧伝したいくらいだったのかもしれない。
理解と共感
学校からの帰路、静子は静一に中学生くらいの頃に同じ事を考えていたと告白した。
静一の言っていた、みんな死んでるくせに、という主張に、まさか静子がここまで理解と共感を示すとは……。
灯り一つ一つに家族がいて、そこでいちいち生活して生きているなんて反吐が出る、か……。
高台から家の灯りを見て、どうしてここまで荒んだ発言をしてしまうのだろう。
普通はもう少し前向きな感想が出てくるシチュエーションだと思う。
なんかこの情報は重要な気がする。
静一の荒んだ発言への理解と共感は、ひょっとして現在の静子の異常性を形作った原因の特定に繋がったりするのかな?
自分は、静子は自分のかつて親子関係を静一との関係で再現してしまっているのではないかとぼんやりと思っていた。
でもよく考えてみると、そういうわけじゃないのかも。
少なくとも静一は静子からの愛は感じているだろうけど、静子は親に愛されなかったと発言していた。だからこそ静一にはそんな思いをして欲しくないから溺愛していると解釈する方が自然か。
静子と静一が本当に生き辛そうで、見ていて可哀そうになる。
高台で抱き合う二人はきっと世間と自分との違い、理解されないし出来ない寂しさや哀しさを分け合っているのだと思う。
「私はずっと、こっち側でいい」
静子はなんでこんなに寂しいことを考えているのか。どうしてそう思うに至ったのか。
おそらく静一も静子の足跡を辿ろうとしている。
先生や小倉母子を残して去る際に、静一が見た彼女たちからの嫌な視線は、先生たちが長部母子に関する悪口で盛り上がっていたのか。それともただ単に静一が、自分たちの悪口を言われていると被害妄想を感じていたに過ぎなかったのかもしれない。
自分達が嘲笑されていると感じることは非常に辛いことだ。
ただ、そうした感情に晒されている時の数少ない味方との関係はより強まっていくのではないか。
静一は今回の話で静子との心の距離がより縮んだことを自覚した。
静子も静一が自分と同じ考えを持っていることを知り、少なからず静一をより愛しく感じたと思う。
でも静子にはまだまだ闇があるようだ。
1話で描写された静一が幼少期の頃、静子と手を繋いで歩いている時に道端で猫の死体を発見した記憶。
これは静子にとって何か都合が悪いということなのか?
幼い静一が覚えていた、静子が覚えていないということは……、まああり得るだろうけど、でも静子の態度は明らかに覚えているけど、この話はしたくない、深堀りしたくないという感じだ。
これは一体静子のどういう心の作用によるものなんだろう。静子のどんな体験、記憶が原因なのかな……。
やはり静子の抱える闇は深い。
そして静一もまた、そんな静子と同じ轍を踏むことになるのだろうか。
以上、血の轍 岱4話のネタバレを含む感想と考察でした。
第65話に続きます。
あわせてよみたい
押見修造先生のおすすめ作品や経歴をなるべく詳細にまとめました。
血の轍第5集の詳細は以下をクリック。
血の轍第4集の詳細は以下をクリック。
血の轍第3集の詳細は以下をクリック。
血の轍第2集の詳細は以下をクリック。
血の轍第1集の詳細は以下をクリック。


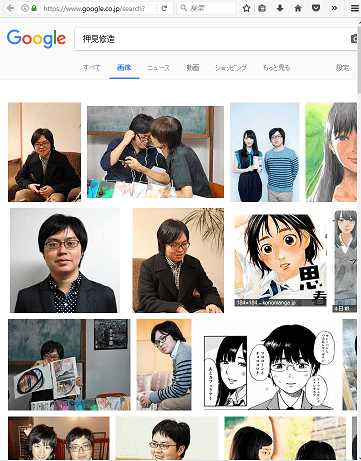








コメントを残す