第16話 乗り替え
※前話”15話”のあらすじのみ。第16話はスペリオール発売後に後日追記予定。
第15話のおさらい
突如長部家の静一の部屋を訪れた吹石からもらったラブレターが静子にバレる。
静一に吹石とくっつくなんて耐えられないと言い、ラブレターを捨てて良いかと問う静子。
静一はそんな静子からの要求に心を乱し、ついには泣き出してしまう。

静子の胸に顔を埋めるようにして泣く静一を静子は強く抱きしめる。
抱き締められて泣くのが収まる静一。
そんな静一をさらに強く抱きしめ、静一も遂には静子の背中に手を回して互いに抱き合う形になる。
静子はそのままベッドに後ろに倒れ込み、静一の顔に自分の顔を近づけて、ごめんね、と謝る。
静一は静子の胸から体を起こし、静子を見つめながら、どこにも行かないで、と懇願する。
静子は閉じていた目を開き、静一を見つめながら、ずっとママの言うことを聞けるかと問い、吹石のラブレターを手に取って一緒に破ることを持ちかける。
静一は静子に抱き寄せられるままに並んでベッドに仰向けになり、二人で手紙の左右を持って真ん中から裂く。
二つに分かれた手紙を静子はさらにもう片方の手も使って一気にビリビリに破く。
目に溢れる涙を止める事もせずに、ただその光景を見つめていた静一。
突然静一は静子に抱き寄せられ、静子と口と口を合わせるキスをする。

幸せそうに笑う静子。
そして静一もまたそんな静子に幸せそうな表情で笑い返すのだった。
第14話の詳細は上記リンクをクリックしてくださいね。第16話
静一の部屋に玄関のドアが開く音と共に、一郎の「静子!?」という聞こえてくる。
忘れ物が見つかったのか、と静子に呼びかけるが返事が無い。
二階にいるのか、と言いながらドンドンと階段を上がってくる一郎。
そして、ノックして返事を待たずに静一の部屋のドアを開ける。
「静一 ママは…」

一郎の目の前に広がっているのはベッドの上に体を横たえる静子と靜一の姿だった。
ビリビリに破られ、バラまかれた紙の中で、静子は静一を抱き寄せている。
唖然とした表情で二人を見つめる一郎。
部屋の中に蝉の鳴き声が響く。
静子は一郎には背を向けたまま、無言で静一を抱き締めている。
静一は涙に濡れた目で一郎を見上げる。

「ど…どうしたん?」
一郎は一体何が起こっているのかわからず、戸惑いの様子を浮かべながら問いかける。
「なんかあったん?」
一郎はベッドの上に落ちている紙に目を留め拾い上げる。
「何だいこの紙?」
じっと一郎を見つめている静一に向かって問いかける。
「なんで破ってあるん?」
静子、と呼びかけながら静子の左肩に手を置く一郎。
「おい…」
静子はムクとゆっくり、上半身だけ起き上がる。

静一は、その様子を身体を横たえたままじっと見つめる。
一郎に振り向く静子。

その心を閉ざし、どこか冷めている表情に戸惑う一郎。
「…な…」
一瞬言葉に詰まりながらも、何? どうしたん? と問いかける。
「大丈夫かい?」
静一は二人のやりとりを、やはりベッドに横たわったまま見つめる。
「忘れ物は?」
静子を見つめながら再び問いかける一郎。
「あったんかい…?」
「なんにもわかんないんね。」
静子は一郎の問いかけには答えず、一瞬見つめる。
「…ふっ」
そして、口元に笑みを浮かべ、笑い始める。
「ふふっ」
一郎は、口を半開きにして静子の表情に見入る。
「あははっ」
静一も笑う静子をぼうっと見つめている。
「私、行がないから。」
目を伏せて静子が答える。
「病院には行がない。ひとりで行って。」

静一は驚いたような表情で静子を見つめる。
「…え?」
一郎もまた驚きを隠さない表情で静子に問いかける。
「何で?」

静子はじっと目を閉じて一瞬の間の後、答える。
「行ったってしょうがないがね。私が行って何か意味あるんかい?」
そんな、と反射的に口に出した後、一郎が続ける。
「何言ってるん? そんなこと無いんべに。」
「…わかんないん?」
静子は顔を伏せたまま一郎に問い返す。
「なんにもわかんないんね。」
静一は静子を見ながらゆっくりと体を起こす。
「私がどんな思いでいたのかなんて、」
一郎を見ることなく、伏し目がちだった静子の目から涙が一筋流れる。
「なーんにもわかんないんだいね。」

後ろ手で支えながら上半身を起こした静一は、見開いた目で静子を見つめる。
静子は、ぐずっ、としゃくりあげたと思うと、ふふふっ、と笑い、はあ~っ、と深く息を吐く。
そしてまた泣き始める。
その様子を言葉もなく見ていた一郎は、わかるよ、と一言声をかける。
「ショックなんだいな…色々…」
「オレもそうなんさ。」

ベッドから上半身を起こした静一は、黙って二人のやりとりを見ている。
「でも…静子のせいじゃない。」
一郎が静子を庇うような言葉を口にする。
静子は黙って一郎の言葉を聞いている。
「みんなもわかってるんさ それは。大丈夫だから。」
一郎は静子を見つめながら声をかけ続ける。
「みんな…わかってるんさ。しげるもきっと…だから…」
鬱積した感情を吐き出す静子。うろたえる一郎。
「何がわかるん!?」
静子が歯を剥き怒りを露わにする。
その様子を驚きの表情を浮かべて見ている静一と一郎。

「何がわかるってゆうん!?」
静子は泣き顔を一郎に向けながら、まるで一郎から静一を守るように両手を横に広げる。
「私達は知らない!! 関係ないから!!」
「パパはさっさと、みんなのところに行けばいいがん!!」
「早くほら!」
挑みかかるような、鬼気迫る表情で一郎に怒りをぶつける静子。
「さっさと行って!!」
静子はそれだけ言って、ふーっ、ふーっ、と威嚇するように大きく息をする。
流れる涙はそのままに、静子は一郎を睨み続ける。

静子の憎しみすら湛えたような眼力に圧され、何も言えなくなる一郎。

「…わかった。」
一郎は、豹変した静子の様子に簡単に折れる。
「帰ったら話すんべぇ。」
どたどたと部屋を出て行き、無言でドアを閉める。
静一はそんな一郎を横目で追う。
そして、静子の背中に目を投じると、ベッドの上に座っている静子は、まるで怒りを吐き出して憔悴したかのように脱力している。
肩を落とし、無言の静子を背後からじっと見つめていた静一は、静子の背中に右手を伸ばす。
「んーっ…」
その静一の手が静子に触れる前に、静子は右手を斜め上に上げて背伸びをする。

そして背後の静一に振り向く。
静一は静子に触れようとして空間に置きざりになった手を戻しもせずに静子と目を合わせる。
「あはっ」
静子は先ほどの怒りがウソのように顔を綻ばせる。
「ママゆっちゃったい。」
静一は無言で笑顔の静子を見つめる。
はー…、と憑き物が落ちたようなため息を一つつく静子。
「お昼どうしよ? お寿司でもとっちゃうかい?」
スッキリしたような笑顔のまま静一に訊ねる。

そして、静一からの返答を待たずに、あ、とベッドの上に散乱した吹石からの手紙に気づく。
「散らかっちゃったんね。そうじきかけなきゃ。」
「ん♪ んん♪」
静子はベッドから立ち上がり、上機嫌で鼻歌を歌いながら部屋の扉に向けて歩いていく。
「んんー♪」
扉を開く静子の背中を何も言わず見つめる静一。

感想
今回の見どころは静子の剥き出しの怒りの表情。
これはぜひ漫画の中で確認して欲しい。

これは目だけのコマ。
実際、1ページ全部使って描かれている顔全体は、その表情から一郎に対する凄まじい怒りと憎しみが静子の心の内に充満していたのが伝わってくる。
単行本2巻が12月に出るけど、多分16話が収録されるのは多分3巻だと思うから未読者はぜひ。
血の轍は各話のタイトルが結構重要な事を示唆している場合が多い気がしている。
そして、今回の「乗り替え」というのも中々考えさせられるタイトルだと思った。
何が「乗り替え」なのか。
多分、静子が完全に夫としての一郎を見放し、代わりに静一に心を移した――――つまり乗り替えたということではないかと思う。
前話で静一は吹石よりも静子を選んだ。
静子は、静一が吹石を恋人として選ぶ事を耐えられないと言い、一緒にラブレターを破れと静一に要求。その結果、静一は見事に静子の望みを叶えた。
しかし一郎はどうか? 4話を読むとわかるが、一郎は静子、あるいは静一よりも親族を選んでいる。
4話の山登りに行く話から本格的に、一郎が明らかに静子ではなく親族側の立場でいる、静子の一番の味方ではないような印象を抱いて、静子が可哀想だなと思っていた。
当サイトの4話の記事にコメントをくれた方の反応からも、やはり静子が明らかに親族たちから疎外されているような空気を感じ取っていることがわかる。
やっぱ4話を読み直してみると気分が悪い。
これって実は日常生活においては普通にある空気感で、悩まされている方はすごく共感できるんじゃないかなと考えている。
自分は親戚付き合いはほぼ無いのでこういう空気に触れることは無いが、何故かすごく分かるんだよなぁ。不思議と。
多分これって家族間、親族間に限らず、ある程度成熟した人間関係のあるところに生じる負の副産物のようなものなんじゃないかな。
全く説明は出来ないけど、いじめの構造にも通じるところがあるんじゃないかな、と思った。
4話では、親族一同で出かけた恒例の山登り(これもそもそも結構珍しくないか?)の途中で、静一がしげるに押されて崖から落ちそうになる。
それを静子が必死の思いで助けたのを「過保護だ」と一蹴し、しげるの母である伯母が嘲笑う。
伯母が嗤ったのにつられるようにして、何も考えずに嗤う祖父母と伯父たち。

そして何より、このシーンで一郎は、親族たちと一緒に嗤う、とまではいかないまでも、親族たちを一切咎める事無く、その場に溶け込むように、同調するように静かに笑みを浮かべるのだ。

そんな一郎の事が、自分はとても残酷に思えた。
静子の立場になれば「危ないだろ!」としげるを叱り、一言、大丈夫だったかと静一や静子に声をかけてやるべきだ。
しかしそんな様子は一切無い。
本来は一番の味方であるべき存在が役目を果たそうとしない。
結果的に果たせなかったとしても、果たそうとする姿勢くらいは見せないといけない。
でも一郎にはそんな姿が微塵も見られない。
しげるの事故を知った後、必死にしげるを救おうと動く一郎のそんな姿勢が静子に向けられていたなら、ひょっとしたらそもそもこんな事態にはならなかったのかもしれないとすら思える。
他の親族からの言葉を無批判に全て受け入れてヘラヘラ笑っている感じというか……。
昭和の頃の、威厳ある父という肖像は今日では完全に無くなってしまい、家長としてのうんぬんかんぬんというのはさすがに時代遅れの感がある。
そういう父親像は時代が求めていないんだから父として弱くなってもしょうがない部分もあるのかもしれないけど、親族から不当に攻撃されている妻や子を守る事すら出来んというのはちょっと庇いようがない。
いや、時代は関係ないな。昭和の父親でも親族にはてんで弱いというのは全然あると思う。
結局は本人の自覚の問題なのかもしれないな……。
静子は今回、メチャクチャにキレた。
ここまで色々書きながらその原因を考えてみたけど、妻である静子や、我が子である静一ではなく、親族にばかり肩入れするような夫にうんざりしたということならこの静子の激昂には男である自分にもわかるような気がする。
しかし、多分、もっと根本的には、一郎本人が静子や静一を守れていないのを”自覚すらしていないところ”にキレたんだと思う。
自覚してない、何も分かってない癖に、

こんな表情されて分かったような事を言われたら、そりゃ静子じゃなくてもキレるわ(笑)。
物語が始まる前から既に関係性は各人の歴史としてそこにある。
これは、物語にリアリティを与える、というよりも、人間を描く上でとても重要な認識だと思う。
それを踏まえて考えると、実は、静子は物語開始時点で既に環境に追い詰められていたのかもしれない。
一郎もそうだけど、そもそも自分の事を陰で、あるいは日向で直接「過保護」だとバカにしてくるような伯母相手に笑顔で対応しなくてはいけないなんて、ストレスを溜めずにいられるわけがない。
2話で早速しげると伯母が登場するが、伯母相手に楽しそうな笑顔を交えて会話する静子は、きっとその心の内で早く帰れとか思って孤独な戦いを繰り広げていたのかもしれないと思うと、読み方が変わる。
自分に対して攻撃してくる親族。一番頼りにするべきはずの夫は守ってくれるどころか攻撃されて苦しんでいることにすら気づいておらずてんでダメ。
一郎の元に嫁に行って以来、特に親戚付き合いにおいては肩身の狭い思いを強いられてきたのではないか? と邪推しなくなる。
そうなると、きっと静子には、支えとなる存在が静一しかいないんじゃないかと思うな。
そういう状況にあって、自分が腹を痛めて生まれた愛しい我が子の存在が過剰なまでに大きくならないはずがない……?
いや、それにしても静子の静一に対する接し方は度が過ぎていると思うんだよな~。
きっともう少し何かこの、静子の「過保護」を産み出した原因があるんじゃないかなと思う。
一郎の頼りなさが静子の静一に対する「過保護」の一因としてあるとして、他にも何かが……。
しげるを突き落としたのは物語の中の時間ではまだ昨日。
犯行以来、静子の本性が読者の前に生々しく露呈する場面が増えた。
今回の話では静子の気持ちがちょっとわかるような気になるけど、でも静子はしげるを意識不明の重体にした犯人なんだよなぁ。
これまでの一郎に対する鬱積した感情が爆発した勢いとはいえ、重傷を負わせたしげるの元に「行ったってしょうがないがね。私が行って何か意味あるんかい?」などと普通に言ってのけるのはヤバイ。
これはもう、しげるを突き落とした罪の意識はあの崖の上に全て置いてきてしまったということではないか。モンスターの誕生だ。
静一に害を与える人間はイコール自分に被害を与える人間だと認識し、反撃してもバレなければ良いとしげるのケースで学んだ静子は、今後、静一のことを諦めきれない吹石にその狂気を向けるかもしれない。
恐ろしい。
今後、しげるが意識不明の重体から生還すればまた展開は一気に変わってくるけど、今、気になるのは吹石だな。
ラブレター破かれたと知ったら悲しむよりもムキになるんじゃないか。
そうなったら静子とぶつかるよね……。こわい……。
以上、血の轍第16話のネタバレを含む感想と考察でした。
次回、第17話は以下をクリックしてくださいね。
あわせてよみたい
押見修造先生のおすすめ作品や経歴をなるべく詳細にまとめました。
血の轍第3集の詳細は以下をクリック。
血の轍第2集の詳細は以下をクリック。
血の轍第1集の詳細は以下をクリック。


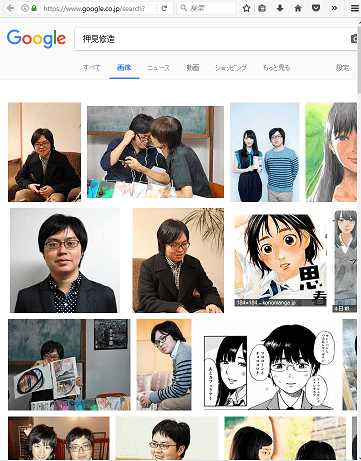





コメントを残す